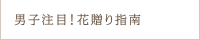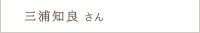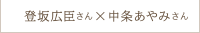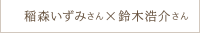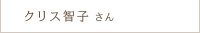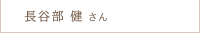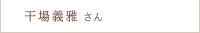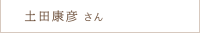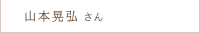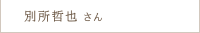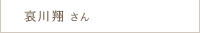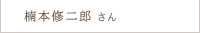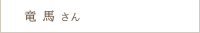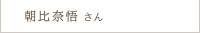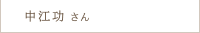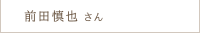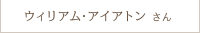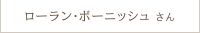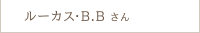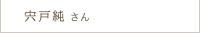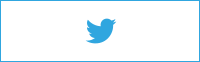2010年に公開された映画「バレンタインデー」は、日本にアメリカでのバレンタインデーの意味を紹介した画期的な映画だった。それを製作し日本で公開したのが、ワーナー・エンターテイメント社。その日本法人で社長を務めるウィリアム・アイアトンさんに、いろいろなお話をうかがった。

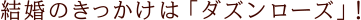
- お父様がアメリカ人で、お母様が日本人というアイアトンさん。
まずはバレンタインデーの思い出について聞いてみたが、意外な言葉が返ってきた。 - 私は日本で生まれて、海外で勤務した4年間をのぞいては日本で過ごしました。大学もインターナショナルな学校でしたが、バレンタインについては特に意識したことはなかったですね。バレンタインだからといって、花をプレゼントした記憶もありませんね。
- とはいえ、奥さまとの結婚のきっかけは「ダズンローズ」との情報を得ている。
早速、なれそめを聞いてみた。 - 当時(1984年)僕は、アメリカに住んでいて、出張でフィリピンに行ったんですよ。たまたま友人に紹介されたのが妻。初めて会った瞬間から、「素敵な方だな」と思いました。彼女はマニラのホテルのアシスタントマネージャーだったので、何度か会いにいったのですがなかなか会えず、その時は帰国しました。ところが、アメリカに帰っても忘れられず、手紙を書いてデートの申込をしたのですが、反応はゼロ。意を決して数ヵ月後に彼女に会いにマニラに戻りました。そのまま勤務先に会いにいったのですが、すでに帰宅してしまったとのことで、がっかりして宿泊していたホテルに戻りました。夜中の1時か2時くらいに、電話のライトが点滅しているのに気づき、メッセージを聞いてみると彼女から「デートはOK」とのこと。初めてのデートは「ポリスアカデミー」という映画でした。
- その後、どうやって遠距離恋愛を育んでいったのだろうか?
- 帰国してからは毎日手紙を書いて送りました。一日に何通も書いたこともあります。そして、毎週1ダース(12本)のバラを贈ることにしたのです。「アメリカン・ビューティー」という真っ赤なバラです。送り先も彼女の家ではなく、勤務先に送りましたよ。そうすることで、まわりの人に「彼女には花を贈ってくれる相手がいるんだ」と、牽制できるじゃないですか(笑)


- さすがの戦略家だ。
しかし毎週バラをフィリピンに送るのは、かなりの出費だったのでは? - 日本で注文をして、支払いを済ませて、届けてくれるのは現地の花屋さんというシステムですが、当時の私の給料からすると、決して安くはなかったですね。だから本当はもっと送りたかったけれど、1ダースがギリギリだったんですよ。ある日、マニラの友人が「いったいいくら払ってるんだ?マニラで直接注文した方が安くなるはずだよ」と教えてくれました。なんと、値段が全然ちがいましたね。それからは、3ダース送ることにしましたよ。
- そうして約半年がすぎ、奥様もついにアイアトンさんの情熱に心が動かされ、ゴールインすることとなったそうだ。
- 彼女の両親はニューヨークに住んでいたので、一緒に会いにいくことにしたのです。その時にセントラル・パークで婚約指輪を渡しました。
- まるで映画のような話だが、何の脚色もない、まぎれもない事実なのだからすごい。
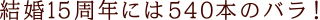
- ある時、「今までバラを何本贈ったかな?」と数えてみたところ、540本だったんですね。ちょうど結婚15周年だったので、せっかくの記念だから、それを一気に倍にしてやろうと思いついたんです。たまたまロンドンの友人宅を訪問中だったのですが、友人夫婦と事前に打ち合わせをして、当日は妻を買い物に連れだしてもらいました。その間に花屋さんに540本のバラを運んでもらって、花瓶にいれたり、床にばらまいたり、部屋中をバラで飾りました。そして、そこに妻が帰ってきて・・・・・・。あれは相当なサプライズでしたね。

- なんとロマンチックなこと!女性にとってはため息のでるような話だ。
- 知人からはよく、「お前はイタリア人やラテンの国の人のようだな」と言われますよ(笑)
- 花贈りに関するエピソードはつきない。ほかにもないか聞いてみた。
- 娘がロンドンの大学に通っていたのですが、一度花を贈りました。
そうしたら、すぐに興奮して電話がかかってきて「生まれて初めて、花をもらった。それがお父さんからで本当に感激した。ありがとう」。私もうれしかったですね。妻も感激したらしく、娘に「あなたは幸せ者ね。だけど、男性を選ぶハードルがあがったわね。お父さんのように花をたくさん贈ってくれて、大事にしてくれる人をみつけなければらならないわね」と言っていましたよ。 - 食事をご馳走してもらったり、物をもらった記憶はいつの間にかあせてしまうが、花をもらった記憶は消えることはない。たとえそれが一輪の花であっても。花は本当に不思議だ。きっと、アイアトンさんのお嬢さんにも一生の記憶として、心に刻まれたにちがいない。
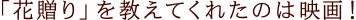
- そんなにスマートに花を贈っているからには、子供のころから花が好きだったのか、あるいは、何かのきっかけがあったのだろうか?
- 昔から花が好きだったわけではないですね。父が花を贈るのを目にしていたわけでもないです。
ただ強いていえばやはり映画の影響ですかね。映画の中には男性が女性に花を贈るシーンがたくさん描かれていますよね。そういうのを見て、自然に身についたような気がします。
実は、うちの父も映画関係の仕事をしていたんですね。その頃はビデオやDVDなんてありませんでしたが、35ミリの映写機があったので毎月映画の映写技師さんがうちに来て、映画の上映会を行っていたんですよ。試写室があるわけでもなく、リビングルームで見るだけでしたが、その頃から映画の魅力にとりつかれましたね。
妻がまだマニラに居た頃、夜のフライトで到着して、夜中に家までいきました。あたりは電気が消えて、チャイムを押すのもはばかれるような静けさ。「映画の中でこんなシーンがあったな」と思いつき、小石を拾って、窓に向かって投げたんですよ。ところが犬を起こしてしまいましてね。犬が途端に吠えだして、彼女だけじゃなくて、近所の人全員を起こしてしまったこともありますよ(笑)


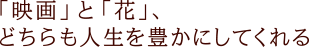
- アイアトンさんの話をうかがっていると、彼の人生には、「映画」と「花」が大きく関わっているような気がしてくる。
- 「映画」と「花」は似ていますね。非常にエモ―ショナルな存在です。感情を刺激したり、心を揺すったり、あるいはその時の気持ちを伝えるものだったり。それがなくても生きてはいけますが、どちらも人生をより楽しく、より豊かにするには、欠かせないものなのではないでしょうか。
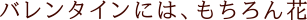
- 最後に、2012年のバレンタインの過ごし方を聞いてみた。
- 妻の誕生日も2月なんですが、「バレンタインデー」、「妻の誕生日」、「結婚記念日」には、今もダズンローズを贈ります。特にバレンタインデーは毎年私がレストランを予約して、二人で食事にいきます。もちろん花を用意して。渡すタイミングはその時のシチュエーションで変えますが、もちろんバレンタインデーには花は必需品です。
- アイアトンさんのように、花贈りの上級になるには経験が必要だが、小さな勇気があれば「花」が人生をかえるきっかけになるかもしれない、ということを教えていただいた。これを教訓に、まずはバレンタインデーから花贈りを始めてみては?
(取材&TEXT T.HAINO)